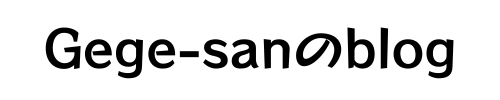会社を退職後に再就職しなければ失業となり、再就職の意思がなければ、そのままですが、再就職希望する場合に、雇用保険に入っていた人は、雇用保険の求職者給付の基本手当つまり失業保険をもらいながら就職活動をするのが一般的だと思います。
その時に、会社都合で退職すると大体中高年の場合は、1年近く失業保険がもらえます。また、教育訓練や職業訓練を受けると受講中はその期間が延長します。
私も失業した時には、ハローワークに行って失業保険を申請しました。失業保険を上手にもらう手続きや実際の対応の仕方を、実際の経験から述べてみます。
雇用保険ですが、公務員などそもそも雇用保険がないという場合は別としても、普通の会社に勤めていれば雇用保険に自動的に入っている場合が多いと思います。雇用保険に加入して保険料を払っていれば、失業した場合には基本手当が支給されます。そこで、注意しなければいけないのは自己都合か会社都合かの退職によって雇用保険の受給手続きや基本手当の受け取りが大きく異なってきます。
まずは、退職後の流れに沿って話します。
会社を退職して、暫くすると会社から離職票が届きます。退職日から1週間から10日程度内に届くことが多いようです。その離職票をもって自分の住所の所轄のハローワークに行きます。ハローワークで受付を済ませ、失業の申請をします。すると、冊子をもらい初回講習の案内を受けます。そして、受付日から待機期間の7日を経た後に、指定された日時に初回講習を受講します。初回講習を受ければ、それが求職活動とみなされます。第1回失業日認定日は、待機期間終了日の約1か月後です。そこで、会社都合で失業した人は、給付制限はないため基本手当の受給が開始します。一方、自己都合で退職した人は、給付制限期間2か月*を経て、待機期間満了後3か月後*からの支給になります。(*なお、R7年度からは給付制限期間1か月を経て、待機期間満了後2か月後からの支給に改正)
基本手当は、前職給与の金額に応じて約80%~50%程度がもらえますが、その前職給与は退職前180日間の平均給与の日額になります。残業も含めてカウントされるため退職前180日つまり半年間は残業を多くこなして給与を上げておくと有利です。もちろん上限があるので、(R6年の場合は)日給が1万7千円程度以上の場合は上限額(日額8500円程度)になったと思います。大体、前職賃金の50%程度はもらえると思います。
失業認定は、初回認定日以降4週間毎に失業認定日が訪れ、その期間に求職活動を2回**行えば基本手当が支給されます。求職活動は、ハローワークでの就職相談も1回にカウントされるので、失業認定日に就職相談をすれば求職活動1回になります。あと1回は、転職エージェントの求人情報に応募するなり、セミナーに参加するなどすれば1回にカウントされます。もちろん、失業認定日のほかに、もう1回ハローワークに就職相談に来てもよいし、ハローワーク経由で求人に応募するのでもよいです。要はハローワークが認める求職活動を2回以上**すればよいわけです。(**なお、R7年度からは求職活動は1回でよいことになった。)
就職相談の内容は簡単なものでOKです。例えば、自分の希望する条件の求人情報を印刷してもらい、どのような求人があっているか係官に相談するだけでOKです。もし、本当に気に入った条件があれば応募すればよいです。
基本手当の支給期間ですが、年齢にもよりますが、私の場合は雇用保険の加入期間が長く、会社都合での退職だったので、330日の受給が決定されました。これは11か月、殆ど1年です。
基本手当は毎月基本的に28日分支給されます。非課税なので、支給額が手取り収入と考えれば、それなりの金額になります。これと退職金があれば、まずは当面の生活に不自由はないでしょう。しかし、失業期間中でも国民健康保険料や住民税、国民年金などは支払わなければなりません。しかも、国民健康保険料の会社負担分がなくなり以前の2倍の額になり、前年の収入に基づいて計算される住民税の請求が来たりするので、かなりの出費を強いられることになります。ただし、会社都合で失業した場合は、国民健康保険料の割引もあります。
失業保険では以下の注意すべきことがあります。受給中に、1日4時間以上の労働をするとその日はもらえなく、ある金額以上の収入を得るとその日は支払われなくなります。また、週20時間以上の労働をすると就職したことになるから失業保険自体ももらえなくなります。失業保険自体は期限が1年なので1年を過ぎるともらえなくなります。ただし、例外があって、職業訓練校に通っている場合は、その期間は延長される特典があります。
|
|